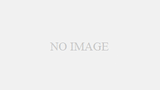浮き沈みの激しいビジネスの世界、昨日まで勢いのあった会社、人物がちょっとしたつまずきで、地に落ちていくことってよくあることです。そんな中、処世術を教えてくれるのが三国志です。
三国志が初めての方も、もう読んだ方も、ビジネスという視点から読むと新しい視点で三国志を読むことができます。ビジネスに転用してこそ、仕事に役立つことできるのです。人民の心をつかみ、天下をとる。結局ビジネスも同じことで、顧客の心をつかみ、シェアをとることだからです。中国乱世、武将たちがどのように戦ってきたのか参考になる部分が多いと思います。
※本文は、吉川英治の三国志から引用しています。
目次
天機をつかむ母の言葉
劉備の母親が煮え切れない息子へ言った一言。これを機に劉備は決心し張飛を受け入れることにする。
「時期というものは、その時をのがしたら、またいつ巡って来るか知れないものです。–何やら、今はその天機が巡って来ているような気がするのです。些細な気持などに囚われずに、お誘いをうけたものなら、張飛どのにまかせて、行ってご覧なさい」
チャンスがやってきたら、天が与えてくれた機会だと信じて、思い切った行動をしなければいけない。思い切った行動ができない原因は、あとから思えば本当にどうでもよい些細な事が多いです。この道は間違ってないと解っていながら勇気がなくて動けないときは、この言葉を思い出したいと思った。それにしても、いつの世も母親は強いものです。
時流にのる
三国志を読んでいると、簡単に兵を集めたり、トントン拍子で馬や軍資金を集めてしまうことがよくあります。最初はたった3人(劉備、関羽、張飛)で事を始めたのだけど、兵、金、武器、何もない状態で関羽が手紙を書いて若者たちに渡したところ、四、五日うちに七八十人も集まったという場面がある。もちろん将の人徳によるものも多いが、それだけではないようです。
商人の張世平は劉備たちの壮大な計画を聞いて、すぐに持っていた五十頭の馬を渡した。関羽はあまりにあっさりと馬を渡したので逆に疑いをもったが、張世平は笑いながらこう答えた。
「私は、あなたの計画を聞いて、これがあなたがたの夢ではなく、わたしども民衆が待っていたものであるという点から、きっと成功するものと信じております。」
ビジネスや商売では時流にのるという言葉をよく使うけど、「時流」とはまさに、人々が望んでいるものが流れとなって動いていることで、劉備たちは、時代の流れにのって、兵を集め、金を集めることができました。どの時代でも人々は腹の中に不満の種をもち、誰かがその不満を取り除いてくれると期待しているのかもしれません。現代でも不満、不安を理解し、それを取り除くことができる人物こそ、大成ができるのはないでしょうか。
困難も選択肢に入れる
困難そうに見えることでも、試しにやってみたら意外にすんなりとできたりする。例えば一人で海外旅行をする時、言葉が通じなかったら、泥棒にあったら、病気になったら・・・。一種の思い込みなんだけど、三国志にも同じような場面がある。賊軍の将、張宝が山峡の絶顚に陣をはっており、劉備たちは苦戦を強いられてた。そんな時、戦術にはとんと無関心だった張飛が言った台詞である。
「登れようか、あの断崖絶壁へ」
「登れそうに見える所から登ったのでは、奇襲にならない。だれの眼にも、登れそうに見えない場所から登るのが、用兵の策というものであろう」
張飛にしては、珍しい名言を吐いたものだ。そのとおりである。登れぬものときめてしまうのは、人間の観念で、その眼だけの観念を超えて、実際に懸命に当てってみれば案外易々と登れるような例はいくらもあることだ。
結果、みごと敵の将、張宝をしとめるのに成功する。あの崖は無理だからと、みんな思い込んでいた。もし登りきれば形勢いっきに逆転するのに、崖を登るという選択肢は張飛しか持っていなかった。どんなときでも、もしこれが出来たらどんな事ができるだろう?という想像力が必要だと思います。どんな困難なことでも試すという選択肢に入れておく。案外簡単に物事が進むかもしれません。
曹操の先を読む力
先を読む力はとても大事な能力です。曹操は、この先を読む力を使って上へ上へと登り詰めたのです。ある行動を起こす事によって、次はどう物事が動いていくのか?世の中の動きに敏感であった。
袁紹が何進に、宮廷をむしばむ宦官たちを一気に葬り去るために、地方の諸侯たちを呼ぶようにと進言していた。それをたまたま聞いた曹操が言った台詞だ。
曹操は、独りせせら笑って、 「ばかな煽動する奴もあればあるものだ。癌は体じゅうにできている物じゃない。一個の元兇を抜けばいいのだ。宦官のうちの首謀者を抓んで牢にぶちこめば、刑史の手でも事は片付くのに、諸方の英雄へ檄を飛ばしたりしたら漢室の紊乱はたちまち諸州の野望家の窺いを知るところとなり、争覇の文脈は、諸方の群雄と、複雑な糸をひいて、天下はたちまち大乱になろう」
結果、曹操が言ったように世の中は大乱へとなるが、ある決断をする事によって、世の中がどう変化していくか、曹操ははっきりと眼に見えていたのでしょう。そういう時代を読む力は現代でも重要で、もし資質のないリーダーの下についたなら、命まではとられないものの、大変な苦労をするのは間違いないです。感情や目先のことばかりにとらわれずに、自分の行動が、世の中(周囲)にどう影響をもたらすのかを常に考えなければならないと思います。
劉備の忍耐力
同盟を結んでいた呂布に裏切られ、城を乗っ取られたあとも、ジッと耐え忍ぶようにと劉備が部下に向けて言った言葉だ。
「身を屈して、分を守り、天の時を待つ。—蛟龍の淵にひそむは昇らんがためである」
蛟龍(こうりゅう)の意味は、中国の竜の一種、あるいは、姿が変態する竜種の幼生だとされる。劉備の言葉は、「蛟龍が水中にひそむのは、時が来れば昇り龍となるためである」ということである。実際、その後、劉備は蜀を建国することになる。呂布のように出たとこ勝負で戦いを挑んでいると自滅の道をたどることになっていたでしょう。転機ではないと判断したら、ジッと耐え忍ぶことも大切なことです。それが何年にもなろうとも、使命は決して忘れず機会を待つ。劉備も軍師の諸葛亮孔明に出会うまでは、ほとんど負け戦ばかりしていたのだから・・。
周瑜の名言
兄、孫策が26歳で早世して、急遽、弟の孫権が呉を継ぐことになった。孫権は兄の死をいたみ、哭いてばかりいた。そんなとき、孫策とは義兄弟で、のちに赤壁の戦いで活躍する周瑜(しゅうゆ)がやってきて、次の言葉を言った。
「何事も、その基(もと)は人です。人を得る国は昌(さかん)になり、人を失う国は亡びましょう。ですからあなたは、高徳才明な人を側らに持つことが第一です」
呉は人材があふれているといわれ、孫権はうまく人を使い呉は発展していく。後に、周瑜は、大督(前線総司令)として、赤壁の戦いで曹操の大軍を打ち破り、孫権も三国の中でも活気にあふれる呉の皇帝に即位することになる。
現代の会社組織も、全く同じで人をうまく配置していくことで発展していく。周瑜の言う「高徳才明な人」はなかなか見つからないかもしれないけど、各人の得意なことをベースに組織を構成していくことは大切です。
「高徳才明な人を側らに持つこと」は、個人にも当てはまる。劉備が孔明に出会って、自分の行くべき道を見つけたように、ある出会いが、人生を大きくかえる岐路になることがある。人はひとりでできることはたかが知れているし、「ああ、あのときあの人に出会ってなかったら・・」という恩人もいるでしょう。そして今からも、この人は!と感じたら、恥ずかしがらずに懐に入っていく勇気が必要です。
▼読んだ方も、まだ見てない方も、ぜひ読んでみてください!