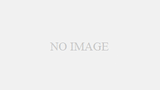初めてドラッカーの本を手にとったのが確か20代の半ばでした。人に勧められて読んだけど、正直、ピンとこなかった。
先日、ある記事でユナイテッドアローズの創業者が「いろんな経営書を読んだが、経営に関しては、ドラッカーに尽きると思っている」というような記事を読んで、あっ、ドラッカーをもう一度読んでみよう!と思ったのでした。
「プロフェッショナルの条件」から引用します。
組織がうまく回るための条件
組織の使命は一つでなければならない。さもなければ混乱する。それぞれの専門家が、自分の専門能力を中心に働くようになる。自分たちの専門能力を共通の目的に向けなくなる。
生産性を向上させるには?
知識労働の生産性の向上を図る場合にまず問うべきは、「何が目的か。何を実現しようとしているのか。なぜそれを行うのか」である。
今、読むからわかる。ある程度仕事の経験を積むと、様々な問題と本の解決策を照らし合わせることができ、自分の中で消化できる。なぜ、スタッフと意見の食い違いが起こるのか?今取り組んでいる仕事は無駄ではないのか? など、そもそも何のための仕事なのかを、一度考えてみることが大事です。
成果を上げる人の共通点
成果をあげる人に共通しているのは、自らの能力や存在を成果に結びつけるうえで必要とされる習慣的な力である。企業や政府機関で働いていようと、病院の理事長や大学の学長であろうと、まったく同じである。私の知るかぎり、知能や勤勉さ、想像力や知識がいかに優れていようと、そのような習慣的な力に欠ける人は成果をあげることはできなかった。
私の知る限り、成果をあげる人は、外向的な人もいたし、内向的な人もいた、はずかしがりやの人もいたし、過激な人も、順応的な人も、心配性も、気楽な人など様々なタイプがいましたが、ドラッカー曰く、成果あげる人の一つの共通点は、習慣的な仕事ができる人であるとのことです。要するに、行き当たりばったりの人間は成果をあげることは出来ないということです。
貢献に焦点を合わせる。
成果をあげるためには、貢献に焦点を合わせなければならない。手元の仕事から顔を上げ、目標に目を向けなければならない。「組織の成果に影響を与える貢献は何か」を自ら問わなければならない。
「どのような貢献ができるか」を自問しなければ、目標を低く設定してしまうばかりではなく、間違った目標を設定してしまうと、ドラッカーは述べています。何をもって貢献とするのか?組織への貢献であり、顧客への貢献です。成果をあげられない原因は、貢献ではなく、権限に焦点を合わせている。つまり、組織の中で権限を守るために保守的な行動に走ったりすることはよくあることです。これでは個人としても、組織としても成果をあげることはできないでしょう。
長い歴史のうちで仕事に選択肢はありませんでした。与えられた仕事だけこなし、自分に何が合っているかなんて考えもしなかったはずです。しかし現代は、多種多様の仕事があり自由に仕事を選べる。そんな時代、仕事によって成果をあげるには、各個人の強みにあった仕事を選ぶ必要性がでてきました。学生時代から、自分の適正に悩む学生が如何に多いことか。ドラッカーは仕事をこなしていく中でしか、強みを見つけることは出来ないと言っています。
強みを知る方法は一つしかない
強みを知る方法は一つしかない。フィードバック分析である。何をすることを決めたならば、何を期待するかをただちに書きとめておく。九ヶ月後、一年後に、その期待と実際の結果を照合する。私自身、これを五〇年以上続けている。そのたびに驚かされている。これを行うならば、誰もが同じように驚かされる。
こうして二、三年のうちに、自らの強みが明らかになる。今日は「強みを知る」ことについて書いてみました。強みとは他人よりもうまく出来る自分自身の特性のようなもので、実践のなかでフィードバック(反省)しながら発見するしかありません。フィードバック分析をするには記録する必要があります。書いたら終わりではなく、過去と現在を見比べる作業をして、足りない部分を補強することが大切です。だけど、分かっているはいるけど、なかなか出来ないのがフィードバック分析・・・(自分がただ怠けものだからかもしれないけど)
時間管理について様々な本が出ていて、自分も限られた時間を有効に使おうとそんな本を何冊も読んできました。だけど「プロフェッショナルの条件」 の下の箇所を読んで、タイムマネジメントの本はもう必要ないのではないかと本気で思ってしまった。なぜなら、タイムマネジメントの要諦は、この部分に集約されているからです。
これで100%時間管理できると確信した
私の観察によれば、成果をあげる者は仕事からスタートしない。時間からスタートする。計画からもスタートしない。何に時間がとらわれているかを明らかにすることからスタートする。次に、時間を管理すべく、自分の時間を奪おうとする非生産的な要求を退ける。そして最後に、その得られた時間を大きくまとめる。すわなち、時間を記録し、管理し、まとめるという三つの段階が、成果をあげるための時間管理の基本となる。
そう、ドラッカーの観察は正しい。さらに「継続して時間の記録をとり、その結果を毎月見ていかなければならない」と述べています。(最低でも年に二回ほど三、四週間記録をとるべきとのこと)
時間管理について様々な本が出ていて、自分も限られた時間を有効に使おうとそんな本を何冊も読んできました。だけど「プロフェッショナルの条件」 の上の箇所を読んで、タイムマネジメントの本はもう必要ないのではないかと本気で思ってしまった。なぜなら、タイムマネジメントの要諦は、この部分に集約されているからです。
まとめ
久しぶり読みなおしてみると、ひっかかっていたものがスッととれたような爽快感がありました。仕事術の本はたくさん世に出ているけど、それらを一つにまとめるとこんな感じになるのではと思ってしまう。自分の考えをまとめると「考えて、書くこと」が仕事であると思いました。考えて、書いたことを実行するのは、「作業」。今、仕事をしているのか、作業をしているのかいつも自問自答したいと思います。