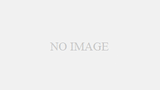売れるための方法が書いてあります。
商売で一番難しいことは、ズバリ売れ続けること。一生懸命、頭を捻って考えた企画商品がまったく売れなかったり、また一時的に売れても、すぐに売れなくなったり、売れ続けるとはどういうことなのでしょうか?その答えが「おはぎ」にあるかもと期待して読んだのが、この本です。表紙には、おはぎがドンっと載っています。
仙台・秋保温泉にある小さなスーパー「主婦の店・さいち」は、社員15名、おはぎとお惣菜をメインに常識を覆す戦略で年商6億円売り上げている会社だです。人口4700人の過疎地にあるこの店で、おはぎが1日平均5000個、お彼岸の中日には2万個売れるそうです。また、300種類を超えるお惣菜も販売。年商6億円のうち、おはぎとお惣菜の「惣菜部門」が売上の50%を占めるという。「さいち式・非常識経営の13か条」を守って経営をしているのとのこと。
1 売れる商品に特別な素材は必要ない
2 チラシは打たない
3 職人は採用しない
4 化学調味料、添加物は使わない
5 レシピ・マニュアルは必要ない
6 経営ノウハウは出し惜しみしない
7 「アナログ閻魔帳」の効用は、エクセルでは見えない
8 取引先と価格交渉はしない
9 倉庫は持たない
10 ロスゼロの計算で、売れ残りは計画に入れない
11 誰も見向きもしない「規格外」を無駄にしない
12 支店は出さない
13 同業他社はライバルではない
(以上アマゾンから抜粋)
チェックポイント
秋保おはぎは昔ながらのおはぎで普通のおはぎに比べてずっと大きいのですが、値段は1個105円で販売しています。お惣菜も普通ののお店に比べると驚かれるほど安く販売しています。どんなに原材料が上がっても不景気でお客様の収入が増えないうちには値上げはしないというのがさいちの原則です。それでも無駄を徹底的になくし売れ残りや廃棄をほとんどゼロにすることで逆に利益が上がってしまうのです。
お惣菜は当時どのスーパーでもまだ扱っていませんでしたし何より味が勝負でしたから他店との価格競争にまきこまれずに済みます。なんとか利益を得るためにはやらざるを得なかったという面もあったのです。メニューは特別なものは全くありません。普段ご家庭で食べているものをより美味しくそして食べやすい形で提供することだけを考えてきました。例えばお新香は一切れ10円で売ったり豆腐も一人暮らしには大きすぎるので4分の一に切って削り節と醤油をおいておくとポンポン売れて行きました。そうしたことはどの店もやっていませんでしたが商品というのはちょっとした工夫で売れるものなのだと良くわかりました。
たとえ一点でも手間をかけてつくるのが私たちの様な小さな店がやるべき本来のこと。逆に大きな店にはなかなかできないことだと思います。
お客様に率直に相談しいつもコミュニケーションをとって、どんなものが食べたいのかを徹底的に考えてきたからではないかと思います。
まとめ
読後、「本物の商売」ってこうなんだよね、と改めて身が引き締まる思いがしました。お客さんの要望に答えながら創意工夫を繰り返していく。ある意味単純で、当たり前な事なのだけど、小さい事をコツコツと習慣として積み重ねていく、そんな努力を数十年されてきた結果の賜物だと感じました。売れ続けるとは、そんなバックグラウンドがあるからこそ成り立つのであって薄っぺらな売上アップ戦略なんて、意味のないものです。